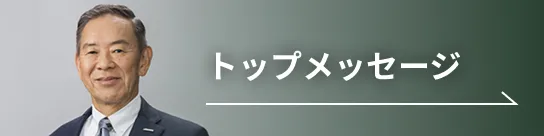ピープル
2nmという困難を乗り越えた先に差別化技術がある
Rapidusは2025年7月18日、2nmプロセスを使ったGAA(ゲート・オール・アラウンド)トランジスタの試作ウェーハを公開した。2024年12月にオランダから空輸でEUV(極遠紫外光)リソグラフィ装置を搬入してから3カ月余りで、EUV装置を稼働させパターン描画の作成に成功。6月には最初のロットを投入し、そのGAAトランジスタ形成ウェーハを7月のカスタマーイベントで披露。このスピード感こそがRapidusの強みだといえる。会社設立の経緯と、3周年を迎えた今の想いを取締役会長である東哲郎に聞いた。
――2020年12月の国際半導体製造装置・材料の展示会SEMICON Japanのパネルディスカッションにおいて技術立国日本の復活について話をされました。あれからわずか1年半余りでRapidusを設立されました。2022年8月Rapidus設立までの経緯について教えてください。

実は2020年夏にIBMからGAAトランジスタを使う2nmプロセスを日本でやらないか、という打診がありました。そこでまず日本の半導体メーカーに相談してみた所、そこまでは手を回せない、という回答で、先端ロジックを既存の日本メーカーが手掛けることは難しいと感じました。
かといって、新たに会社を設立して1社だけで達成できる話ではありません。最先端の半導体が入手できなければ日本としても大変なことになる、という危惧を抱くようになりました。
半導体ビジネスを始めるためには、技術、人、資金が必要です。まずは技術の確認です。東芝と一緒にNANDフラッシュメモリを生産しているウェスタンデジタルジャパン社長(当時)の小池淳義に連絡し、GAA2nmプロセスが技術的に可能かどうかの検討を依頼しました。人材については1年間の検討の中で、日本と世界にいる人たちをリストアップしました。
その当時、国はTSMCの九州への誘致も進めていましたが、TSMC熊本では22nm/12nmの半導体製造ラインですが、2nmプロセスにはほど遠い。そこで2022年8月にRapidusを設立しました。
会社設立当初の段階では国からのご支援によって開発を進めることを計画していたため、半導体製品を利用するシステムメーカーが2nm技術に関心があることを示す必要がありました。8月から10月までの間に関連する日本の有力企業を回りました。その結果、8社が出資してくれました。
実際に2nmプロセスを進めるためにはEUV装置を入手しなければなりません。同年夏にオランダのASML社のトップと話をして日本に納入していただきたいとお願いしたところ、快諾してくれました。そして11月に発表にこぎつけたという次第です。
――2025年8月で創立3周年になりますが、今の時点でのRapidusへの想いを語ってください。
これまでスケジュール通りに進めています。工場の起工式を2023年9月に行った直後から建設を始めました。建設は目覚ましい速さで順調に進み、2024年12月には製造装置搬入を開始、3カ月後には200台以上の装置を導入しました。4月1日には露光できるレベルになってきたことを示すため、EUVで描画したパターンを示しました。さらに6月に最初のロット投入を実施。そして7月のカスタマーイベントでは試作ウェーハにおいて2nmノードのGAAトランジスタの動作を確認できたことを報告しました。今後、サンプルの完成度を高めていき、順次顧客に評価してもらう予定です。
これだけを振り返るとスケジュール通りかもしれませんが、これまでの成果を出すための社員のスピード感はすさまじいものがあります。例えば通常は、EUV装置を搬入してからパターン描画まで通常半年近くかかりますが、それを3カ月でやってのけました。

設立当時十数人しかいなかった社員は今や800名となり、派遣社員も含めると1,000人を超えています。毎月30~40人の社員が入ってきて働いています。平均年齢は比較的高めですが、長年半導体プロセスに関わってきた人たちなので、使命感もやる気も高く、楽しそうに仕事しています。Rapidusに対する期待も高まっています。約150名を米国ニューヨーク州アルバニーにあるIBMの拠点に派遣し、2年間GAA技術のトレーニングと量産開発を共同で進めてきました。このうちの半数が千歳に戻ってきました。アルバニーで行ってきたGAAトランジスタを使った2nmプロセス研究の成果を、千歳に早期に移管していきます。創立3年でこれからの大きな土台が出来てきたと言える段階です。
彼らと話をすると、「自分達は一緒に研究してきたIBMに伍していける」、というような意識で帰ってきていることがわかります。私はそれを非常に頼もしく感じます。こうしてこの会社に入ってきた人たちによって我々がやろうとしたことが実現できる格好になってきたというのは、大きな変化のひとつだなという風に思っています。
――設立当初から現在は半導体に対する環境は変わってきています。特にAI(人工知能)の進展が大きく変わりました。
AIの進化が急速に進み、AIから生成AIへと進化し、それに必要な半導体が求められるようになりました。今はAIデータセンターへの需要が高まっていますが、これからはエッジやエンドポイントでのAI、すなわち生活レベルでのAIの時代へと突入します。例えば、第1次産業(農業や漁業、酪農)にAIを活用することで、生産効率が上がります。わたしが講演会で登壇した際に聞いた話なのですが、私たちが事業を立ち上げようとしている地元北海道の若い酪農家は起業家の視点で北海道の産業を何とかして発展させようという気持ちに溢れています。例えば欧州の高級なアイスクリームには北海道の牛乳が使われています。彼らが切磋琢磨しながらいろいろとアイディアを出し合い、北海道とAIを結び付けていくと新しい次のステージに入りやすいと思います。

昔、明治維新以降、本州からどんどん人が北海道に移っていって開拓し、産業を発展させていきました。Rapidusが北海道に半導体工場を作り、それが弾みとなって、それと同じようなことが起こると、私たちだけでなく北海道にとっても意義のあることになるんじゃないかと思います。北海道大学に行って色々話したり、現地の学生のプレゼンテーションも聞いたりすると、やはり最後にクラーク博士の"Boys, be ambitious!" の像が出てきます。やはりそういうBoys, be ambitiousと言う精神が受け継がれていると思ってます。
シリコンバレーでは半導体関連企業を誘致し、そこに教育機関が企業の成長をサポートする役割を果たした。その結果、病院をはじめとするインフラが整い、国内外から人々を受け入れやすい環境を整えました。北海道も自治体をはじめ、北海道外から北海道に移り住み、その人たちが働きやすい環境を整備することに対して積極的なので、とても期待しています。
――日本の半導体にとってRapidusの役割とはなんでしょうか?また、ニッポン半導体への思いと未来への期待を教えてください。

半導体は経済安全保障上の観点でも重要となっているため、最先端の半導体を扱うRapidusの必要性は高まってきます。先端半導体を持っていることで、地政学上有利に働くことは間違いありません。
Rapidusは、16nm~3nmのFinFET技術を抜かして、いきなり2nmプロセスという最先端の世界に飛び出しましたが、Rapidus設立時は結構、日本の中でも『こんなに飛躍したものができるのか?』というような疑問や、段階を踏まずに一気に最先端の技術に飛んでしまうことへの不安と言うのがありました。私はそれを、"振り子モデル" で考えています。振り子は最も上に来た時にスピードがゼロになります。最も下に来る時が最大のスピードになります。技術やビジネスが最も激しい状態を表しています。スピードが最大値の時に入り込むことはビジネス的に難しい。なので私たちはスピードがゼロになるゲームチェンジのタイミングで参入するのです。私たちのようなスタートアップでの2nm技術開発は大変ですが、成功すればビジネス上は有利になります。またこれからの半導体は、汎用品から専用品になると思います。それは消費電力の観点からも必然です。汎用のCPUは使わない機能が多いのですが、その機能にも電力が使われてしまっています。専用半導体は必要な機能に絞っていますので、無駄な電力が少ないのです。

ニッポン半導体に対して、日本はやればできるという希望を示したいのです。Rapidusが成功すれば、今後新しいことに挑戦する若い人たちに勇気を与えられます。新しいことに挑戦する場合、必ず困難が訪れます。これを乗り越えると差別化技術が生まれます。失敗を恐れずにやることはやりがいをもたらしてくれます。中途入社したベテランエンジニアたちは、かつての日本の半導体を知っています。退路を断って入社した人たちなので、働く意欲はすさまじいです。その人たちのエネルギーや意欲がRapidusに入ってくる若い人たちにも伝承されて、また次につながってくるという格好になります。若年層の社員もどんどん増えていますが、こういう環境に身を置くのはものすごいラッキーだと思います。
そのために、若い人たちが失敗しても、そこから何かを学び、次の仕事への活かす、という企業風土を作れば意欲は削がれません。失敗を恐れず挑戦する姿勢を企業が若い人に示すことは極めて重要ですし、そういうような社風を作っていくというのは極めて重要であると思います。
- #インタビュー
- #東哲郎
- #GAA
- #AI