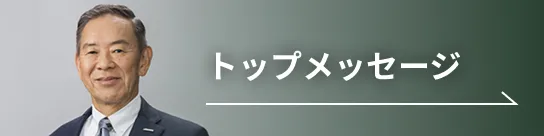ピープル
世界最先端2nm半導体を製造するIIMのリアル。魂のロットに込められた想い
2025年7月18日、世界最先端2nm半導体であるGAA(Gate-All-Around)トランジスタの動作を確認したと発表したRapidus。しかし、現在、パイロットラインが構築されている北海道千歳市のIIM(Innovative Integration for Manufacturing)の中に入れるのは限られた人のみで、そのリアルを知る者は少ない。そこで、代表取締役 専務執行役員 オペレーション本部長の清水敦男に現場のリアルを聞いた。
IIMの構想と建設、パイロットライン立ち上げまでのマイルストーン
――GAAトランジスタの動作確認まで、光のような速さで開発を進めてこられました。会社設立からここに至るまでの軌跡について教えてください。

IIMの建設において印象に残っているのは、2023年9月1日に開催した起工式です。これ以降、IIMは見る見るうちに外観ができあがり、現在(2025年9月)までまさに突っ走ってきました。そして、昨年12月には回路パターンの露光を行うEUV露光装置をIIMに搬入しました。
ここまでオンタイムでマイルストーンを達成してきましたが、次々と課題が発生するため一段落ついたタイミングはなく、常に課題をクリアする状況が今後も続きます。
――現在、IIMのなかでどのようなことが行われているのか、現場のリアルを教えてください。

EUV露光装置搬入後にも、パイロットライン構築に必要な装置を200台以上搬入して立ち上げ、試作の準備を進めてきました。完成した試作品を、お客様を始めとするステークホルダーの方々に披露したのが、2025年7月18日に開催したカスタマーイベントです。
試作品をものすごいスピードで生産できること、そして動作を確認できたことは大きな一歩でした。
設備を設置して、ただつなぎ込めば生産できるようになる訳ではありません。最先端のアプリケーションの調整など設備メーカーの方々の協力が必要です。また、IBMから技術供与を受けましたが、特性(性能)向上など量産に向けて「どのようにすれば目標を達成できるだろうか?」と、自分たちで日々頭を抱えながら課題を解決しています。
試作品製作を通して見えたエンジニアの姿
――現場の方々はどのように試作品製作を成功させ、現在、どのような気持ちで仕事をされているのでしょうか。

社長の小池は一番最初の試作品のことを「魂のロット」と呼んでいます。魂のロットが完成するまでの間、当時、IIMで働いていた約400人のエンジニアだけでなく本社の社員も合わせて総勢600人ほどの社員が見守っていました。オンタイムで、ものすごいスピードで流動する様子を、皆が自分ごとと捉えて勝負の行方を見守っていたのです。
特に自らが責任を持つ工程にさしかかると気が気でなかったと思います。そのように、数百人の意識がたった一つのロットに集中するというのは、なかなかないことです。
一般的な半導体工場なら、すでに工場が完成して生産設備が整った状態でロットを流します。しかし、我々は建物も設備も、そして人を含むリソースすべてがゼロからの立ち上げでした。そのため、皆が魂のロットに集中し、心を一つにできたのだと思います。
現在はさらに複数の試作を進めています。次々と生まれてくる課題を解決するため、全社一丸となって進めていく姿勢は現在も変わっていません。
世界最先端2nm半導体の量産と短TAT実現のためのカギを握る技術
――2nm半導体の量産と短TAT(TAT:Turn Around Time)(※1)実現のためには、EUV露光装置をはじめ、さまざまな装置が必要です。カギを握る装置について教えてください。

現在、EUV露光装置を製造できるのはオランダのASML社のみです。我々はこの装置を量産機としては日本で初めて導入しました。しかし、ASML社の要望をそのまま受け入れるとなると、設置の数カ月前にはクリーンルームを整備しておく必要がありました。一般的な半導体工場なら、すでに工場がある状態なので問題ありませんが、我々は工場の建設を進めながらEUV露光装置の事前工事を進めなければなりません。
そこで考えたのが、要望(条件)を分解して一つずつ精査することです。例えば、温度や湿度、クリーン度など条件がありますが、EUV露光装置を設置するエリアが要件を満たしていれば問題ないはずです。ASML社と地道な交渉を続け、ものすごいスピードで建設と事前工事を進めた結果、2024年の12月に無事に搬入できました。
一方、短TAT実現のために、我々は新しい搬送システムを導入しました。IIMのような大規模な工場に本格導入するのは世界初です。天井の搬送設備の設置も建設と同時並行で進めました。当時は本当に完成するのかとの不安と、完成後の動作がイメージできずに戸惑いを感じたこともありましたが、現在は無事に稼働しています。
――環境対策にも相当な力を入れているとお聞きしました。なぜ、そこまで力を入れるのか教えてください。

社長の小池は「半導体産業は永続的でなければならない」と常々言っています。人間がさらなる技術の発展を求める以上、先端半導体の高密度化や高性能化は今後も求められていきます。
産業革命以降、特にここ40年ほどは、エネルギーや化学物質をたくさん使って発展してきました。しかし、いつかエネルギーが枯渇したり、化学物質の規制が厳しくなったりして、特定の材料や工程が禁止される可能性もあります。そうなれば我々だけでなく、世界中の半導体メーカーが技術の進歩に対応できなくなります。
それを避けるために、環境に負荷を与えずに事業を継続しなければなりません。それは千歳で事業を行うと決めたときから、小池の頭の中にあったことでした。
しかし、我々の事業が環境に負荷を与えること、ましてや加速させることはあってはなりません。
CO2の排出量にも配慮しています。現在、北海道内にサプライヤーの工場はなく、本州から材料を輸送しています。しかし、サプライヤーが個別に運ぶとCO2排出量が多くなってしまうため、特定の地点に材料を集めて集中配送を実施しています。
いまの想いと次の展望
――今後、どのようなステップで量産に向かうのか教えてください。

2027年の量産開始に向けて、歩留まり(良品率)改善や信頼性向上などさまざまな課題があります。ですが、これは「Rapidus」と刻印された我々の製品が、サーバーをはじめとする様々な機器に搭載され、最高のパフォーマンスを発揮するために必要不可欠です。
少し具体的にお話すると、我々から先行顧客に対して提供する「PDK(Process Design Kit)」(※2)を使って、お客様自身の製品設計の目処を立てられるようにすることが目標です。その中には、我々が開発を進めている半導体開発ツールである「Raads(Rapidus AI-Agentic Design Solution)」(※3)や、我々が製造する先端半導体の性能を示すデータが含まれています。お客様はこれらをもとに製品設計が可能か判断します。
今後も「魂のロット」と同じように、皆が勝負をかけるロットが続きますが、2027年の量産開始に向けて着実に準備を進めていきたいと思います。
――後工程についても伺います。現在、構築が進められているRCS(Rapidus Chiplet Solutions)今後の展開について教えてください。
現在、IIMに隣接するセイコーエプソン様の千歳事業所内において、後工程のパイロットラインであるRCSを立ち上げるべく設備の搬入や立ち上げ、クリーンルームの構築を進めています。後工程で製造する先端パッケージにはチップレット(※4)や3Dパッケージ(※5)など複数の技術があり、すべてに対応できるよう準備を進めています。これらの技術開発を2026年から開始し、2027年以降を目処にIIMでの後工程ライン構築を目標にしています。
Rapidusが目指していく世界
――Rapidusはお客様にとってどのような存在になることを目指しているのでしょうか。また、その挑戦に終わりはあるのでしょうか。

我々の製品が先端半導体の唯一の選択肢になるようお客様に強要することはできません。しかし、現実問題として、2nmプロセスの先端半導体開発に取り組んでいるのは、世界でも弊社を含めて数社しかありません。
弊社は短TATという強みを活かして、より多くのお客様に選択肢の一つとして認知していただけるように努力していきます。
現在では飛行機が空を飛ぶのは当然のことです。かつてはありえないと思われていましたが、人間は発展を繰り返してきました。人間が欲望を持ち続ける限り、先端半導体のニーズは絶対になくなりません。これまで技術の進歩が止まったこともありません。
今後も、技術の進歩が求められる限り、エンジニアは決してギブアップしません。今日のインタビューは、飛行機の音がすると中断しながら進めましたが、そのうち、全く音のしない飛行機が開発されるかもしれません。
我々は、先端半導体の量産レディとなっても、飽くなき挑戦を続けていきます。

- ※1)TAT(Turn Around Time):製品がラインに入って流動を開始してから、完成するまでの時間のこと。短TATを実現するためには、搬送など生産に直接関与しない時間の短縮も求められている。
- ※2)PDK(Process Design Kit):半導体プロセスで回路を設計する際に必要な設計情報やツールをまとめたもの。
- ※3)Raads(Rapidus AI-Agentic Design Solution):AI/機械学習(ML)を活用した半導体設計支援サービスで、設計サイクルタイムの短縮とコストの大幅削減を目指している。
- ※4)チップレット:一つのパッケージ内で複数の機能の異なる半導体を組み合わせて大規模なシステムを構築する技術のこと。複数のロジック半導体を一つのパッケージにまとめるタイプや、ロジック半導体とメモリを一つのパッケージにまとめるタイプがある。
- ※5)3Dパッケージ:複数の半導体を上下に積み上げて実装するパッケージ技術。垂直に設けられたシリコン貫通電極(TSV=Through Silicon VIa)によって半導体どうしを電気的に接続する。
- #インタビュー
- #清水敦男
- #IIM
- #Raads