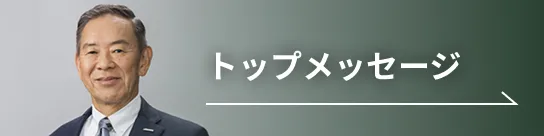テクノロジー
半導体後工程を解説 製品化パッケージングの全貌
半導体はデジタル社会を支える要です。「後工程」と呼ばれるパッケージング技術がかつてないほどの注目を集めています。トランジスタや配線の微細化が性能向上を牽引してきましたが、物理的、コスト的限界が見え始め、今後は高度なパッケージングが鍵になります。
半導体製造は大きく「前工程」と「後工程」に分かれます。前工程でウェーハ上に回路を形成した段階では、チップはまだ完成していません。後工程でチップを切り出し、パッケージングと検査を経て電子機器に搭載できる完成品となります。本記事では、半導体チップが"使える製品になるまでの道のり"を、後工程の主要なステップごとに詳しく解説し、その技術的な奥深さと重要性を解き明かしていきます。
半導体後工程の全体像
前工程では、シリコンウェーハ上に集積回路などの微細な回路をナノメートル精度で加工し、膨大な数のトランジスタを作り込みます。
後工程では、ウェーハ上に作り込まれた個々のチップを切り離して、基板(サブストレート)などと接触させ通電をさせる必要があります。かつては金属の細線を使用したワイヤーボンディングと呼ばれる手法が使われていましたが、現在はバンプと呼ばれる突起状の接続端子を使うフリップチップ実装が主流となっています。
フリップチップ実装では、まずチップの電極上にバンプを形成します。その後にチップをダイシングによって個片化します。そしてチップを反転させてサブストレート上に接合します。接合後にチップとサブストレートの隙間に封止材を充填し、最後に樹脂などで全体を封止(モールディング)します。これらに対してバーンインや電気的特性検査、信頼性試験を行って不良品を取り除き、良品は製品表面にレーザーでマーキングを施して最終的な完成品として出荷されます。

半導体メーカーでは、自社で後工程製造を行う企業もありますが、前工程の製造の多くをファウンドリが担っているのと同様に、後工程ではOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)と呼ばれる企業が専門に行っています。ファウンドリ企業が前工程の製造を担い、OSAT企業が後工程を担う分業体制により、各社はそれぞれの専門技術を生かして効率的に半導体を生産しています。

後工程の主要プロセス
後工程はウェーハ上の多数のチップを製品チップへと仕上げる連続した工程です。その主な工程は以下の通りです。
バンプ形成
チップを個々に切り出す前のウェーハ状態で、それぞれのチップの電極パッド上に微細な突起状の接続端子となるバンプを形成します。形成方法はめっき法やボール搭載法、スクリーン印刷法などがあります。バンプの高さや形状を精密にコントロールすることが重要で、バンプサイズが均一であれば、この後の実装における不良を低減できます。
ダイシング
シリコンウェーハを精密に切断し、個々のチップ(ダイとも呼ばれる)に分割する工程です。ダイサーと呼ばれる装置で数μm(マイクロメートル)の精度でチップを切り出します。
ダイヤモンドブレード(砥石)やレーザーを使って慎重に切断してチップを分離します。欠けや微細な破損が入らないよう、切断条件やクリーンな環境が重要です。
バンプ接合
バンプ接合ではまずチップを180度反転させ、実装するサブストレートの接続部分と位置合わせをします。そしてチップとサブストレートを接合させます。接合には加熱や圧力、超音波などを使って電気的、機械的に行われます。
アンダーフィル充填
バンプ接合後、チップとサブストレートの隙間にアンダーフィルと呼ばれる封止材を充填します。これによってチップとサブストレートの接続の信頼性が向上します。わずかな隙間にエポキシ樹脂を毛細管現象によって浸透させます。
モールディング
チップ全体を樹脂で封止する工程です。専用のモールディング装置でエポキシ樹脂などを流し込み、チップを外部環境から保護します。硬化樹脂は衝撃・湿気・温度変化を遮断し、長期安定動作を保証します。用途に応じて耐熱・絶縁性に優れた樹脂を選定し、均一成形と気泡排除で品質を確保します。
最終テスト
完成品チップは、以下の試験と検査で性能と信頼性を総合的に確認します。
- バーンイン試験:高温・高電圧で通電し、初期故障を加速的に発見・除去します。特にダイナミックバーンインは実動作に近い信号を用いるため、市場投入後の故障リスクをさらに低減できます。
- 信頼性試験:温度サイクルや高温高湿バイアスなどの環境ストレスを与え、長期安定性と劣化メカニズムを評価します。得られたデータは寿命予測や故障解析に活用されます。
- 電気特性試験:常温・高温条件で動作電圧や信号特性を測定し、バーンイン前後の性能変化と規格適合を確認します。
3種類の試験は相互に補完し合い、製品の品質と信頼性を確保する上で欠かせません。加えて外観検査によってパッケージのクラックや欠損を確認し、すべてのテストに合格したチップのみが出荷されます。
Rapidusにおけるチップレットパッケージ技術
Rapidusはセイコーエプソン千歳事業所(北海道千歳市)にクリーンルームを構築し、半導体後工程の研究開発拠点「Rapidus Chiplet Solutions」(RCS)を開設します。Rapidusは、ここで「2nm世代半導体のチップレットパッケージ設計・製造技術開発」をテーマに、自動化を含めたチップレットパッケージの量産技術の開発を進めます。RCSには、FCBGAプロセスを始め、Siインターポーザ・プロセス、RDLプロセス、ハイブリッドボンディングプロセスに対応したパイロットラインが設置され、装置の自動化などを含めた量産技術の研究開発を行う予定です。

複数のチップを一つのパッケージに集積するチップレット技術にも注目が集まっています。積層や2.5D/3D集積で微細化限界を補い、高機能、低消費電力を実現できます。この方式では、チップ間接続を担うインターポーザの性能が鍵であり、要求性能の高まりとともに大型化も進んでいます。Rapidusは、半導体パッケージを複数枚一括生産するためのキャリア基板として業界最大級となる「600mm角パネルレベルパッケージ技術」の開発を進めており、量産性、コスト低減、高信頼性を兼ね備えたインターポーザ製造を目指しています。

半導体の後工程における重要なポイント
製品品質と信頼性の最終保証
半導体の後工程は、これまで黒子のような存在でしたが現代のデジタル社会を足元で支える「見えない品質保証」の役割を担っています。パッケージングされたチップは樹脂に覆われて電子機器に搭載されるため、その中身が目に触れる機会はありません。
しかし、そのパッケージがあるおかげでチップは外部の衝撃や湿度、温度の変化から守られ、長期間にわたり安定した動作が可能になります。このように後工程は、半導体デバイスの品質と信頼性を最終的に保証する門番として機能しているのです。
コスト削減と効率化への貢献
後工程は生産効率やコスト面でも重要な貢献をしています。前後工程を分業する現行モデルでは、ファウンドリが前工程、OSATが後工程に特化し、設備投資を最小化して製造コストを抑制できます。
さらにチップレット技術の活用によって、一つの大規模チップを作るよりも、小さいチップレットでは、同じ製造欠陥発生率でも個々のチップが欠陥の影響を受ける確率が大きなチップより低くなるため、歩留まりを向上できます。歩留まり改善は無駄な廃棄を減らしてコスト低減に直結するため、後工程での工夫が経済面でも大きな意味を持ちます。
パッケージングの進化と多様なニーズへの対応
従来はチップを単に保護し接続する役割だったパッケージが、今や異種集積(ヘテロジニアスインテグレーション)という新たな潮流の主役となっています。異種集積とは、製造プロセスや機能の異なる複数のダイを一つのパッケージに収める技術の総称です。例えば、最新プロセスで製造した高性能ロジックチップと、異なるプロセスで製造したメモリやアナログチップを同一パッケージに収めることで、コストを抑えつつ必要な機能を盛り込むことが可能になります。複数のチップを側面だけでなく垂直方向にも積み重ねる3次元実装技術(3Dパッケージング)と相まって、チップレットによる異種集積は次世代半導体の性能革新を実現する大きな原動力となっています。
まとめ
半導体の後工程は、ウェーハ上のチップを最終製品へ仕上げる重要工程です。ダイシング、組立、封止、テストの各ステップが品質と信頼性を決定します。チップレットなど先端パッケージの進歩で、後工程は性能向上とコスト最適化を決定付ける工程となりました。微細化の限界を補う異種集積がデバイスの可能性を広げ、後工程は半導体産業をけん引する革新分野へと進化しています。
半導体チップを基板に接続するためのパッケージング技術の一つで、その名の通り「フリップチップ(Flip Chip)」技術と「ボールグリッドアレイ(Ball Grid Array)」技術を組み合わせたものです。2つの技術を組み合わせることで、高集積化された半導体の性能を引き出し、高速化や多機能化を可能にします。
ワイヤーボンディングのように半導体チップを側面から金属ワイヤーで接続するのではなく、チップ表面のバンプをパッケージ基板の電極に直接接続する技術です。チップを裏返し(フリップ)にして実装するためこの名が付きました。
パッケージの裏面全体にボール状のはんだが格子状に配列されたパッケージ形式です。これによって多数の入出力ピンを高密度に配置できます。
- #半導体
- #後工程
- #チップレット
- #パッケージ
- #インターポーザ